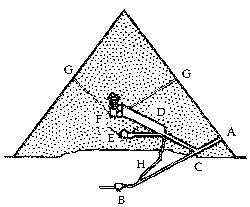墓地には、撒かれてから日の浅い土の上に新参の樫の十字架ががっしりと、重々しく、風化など知らぬ姿で立つ。
四月、どんよりとした日々。だだっ広い郡立墓地の墓碑は遠く離れたところからでも葉をつけぬ木々の間を通して見え、さめざめとした風が十字架の台座に置かれた陶製の花輪を唸らせている。
その十字架はというと、ぷっくりと隆起した陶製の肖像板を嵌め込み、その肖像板には嬉々とした、ぞっとするほど生き生きした眼の、女学生の写真が入っていた。
オーリャ・メシェールスカヤである。
少女時代の彼女は、女学生が着る褐色のコートの群れの中にあっては、これといって目立つ方ではなかった。彼女について語ることがあるとすれば、良家の出で、裕福、それに幸せな女の子たちのうちの一人だということ、優秀だが悪戯好きで、担任の女教師の言うことにはてんでお構いなしだったということぐらいだろうか。その後、彼女は蕾を開き始めるが、数日どころか、数時間単位の成長を見せる。ほっそりとしたウェストに、すらっとした脚の彼女は十四歳にしてすでに、胸そしてあらゆるフォルムが見事に描き出され、その魅力たるやこれまで一度として人間の言葉で言い表されたことのないほどのものであった。十五になる頃の彼女はすでに美少女という評判を得る。一部の友人たちはどれほど念入りに髪を結い、清潔で、控えめな身のこなしに気を配ったことだろうか! なのに、彼女ときたら怖いもの知らずなのだ、手についたインクの汚れも、恥じらいで真っ赤になった顔も、振り乱した髪も、競走で転倒した時に捲り上がる膝のことなどもお構いなしなのだ。いかなる配慮も努力もしない彼女にいつしか訪れたのは、ここ二年間で女学校全体でも彼女を一際目立たせるもの全てだったのだ。それは艶やかさ、堂々さ、軽やかさ、清澄な眼光…誰も舞踏会ではオーリャ・メシェールスカヤみたく踊れなかったし、誰も彼女のようには馬を乗りこなせなかったし、彼女ほど舞踏会でちやほやされる者もいなかったし、それに何故だか分からないが、彼女ほど後輩たちから憧れを抱かれた者はいなかった。いつしか彼女は一端の娘となり、いつしか女学校内での彼女の名声は確固たるものとなったが、そうなるともはや彼女は軽薄で、自分を熱狂するファンなしでは生きられないのではないかとか、男子校生シェンシンが彼女にゾッコンで、彼女もどうやら彼のことが好きらしいが、彼に対する態度があまりにあやふやだったばかりに彼は自殺を図った云々…という流言まで飛び交った。
学生時代最後の冬のこと、オーリャ・メシェールスカヤは女学校内での話題に狂喜せんばかりだった。その冬は雪が多く、太陽に恵まれ、厳寒で、雪に覆われた女学校中庭の高いエゾマツ林の向こう側に早々落ちていく太陽は、明日の日も相変わらずの好天で、光に溢れた冬将軍と太陽を、それにソボール通りの散歩、市立公園での橇遊び、薔薇色に染まる夕べ、音楽会そしてその中ではオーリャ・メシェールスカヤが一番無邪気で幸せに見える、四方八方に滑る橇遊びの人混みを約束していた。そんなある日の長い休憩時間、彼女は講堂内を金切り声ではしゃぎながら追っかけてくる一年生たちから旋風の如く身をかわしていたところ、突如校長からの呼び出しを受けた。走り回っていた足をピタッと止めた彼女は深呼吸を一つだけすると、すでに慣れた女性の素早い身ごなしで髪型を整え、エプロンの両角を肩まで引き寄せると、輝かせた眼で階上へと駆け上がっていった。年の割には若く見えるが、灰を被ったような髪の女校長が編物を手にして書斎机の向こうで静かに腰かけていて、その頭上には皇帝の肖像画が掛かっている。
「ごきげんいかが、マドモワゼル・メシェールスカヤ−」校長は編物から目を上げずにフランス語でこう言った。「残念ですが、わたくしがあなたの素行についてお話しするのにわざわざここに呼び出すのはこれが初めてじゃありませんよねぇ。」
「はい、マダム。」メシェールスカヤは机に歩み寄り、校長の方にじっと目を凝らしたが、顔に別段表情を出さずにこう答えると、彼女だけが出来る軽やかさと優雅さで腰を下ろした。
「私が注意したところであなたは上の空でしょうね、残念ですが、これだけは確信してます。」こう言って校長は糸を引っ張り、ニスのかかった床の上で毛糸の玉がころりと転がると、それに好奇の視線を送ったメシェールスカヤは、またそこで視線を上げた。「二度としません、声を張り上げたり喋ったりいたしません。」彼女はこう言うのだった。
メシェールスカヤには、厳寒なモロースの日に見事なオランダ風ペチカの温もりと書斎机のスズランの爽快さをすっかり吸い込んだこの異常なほど清潔で広々とした校長室が大のお気に入りだった。どこかの煌びやかなホールの真ん中に全身像で描かれた若き皇帝に目を向けてから、乳白色で、丁寧にウェーブをかけた校長の髪の均等な分け目を見ると、何かを待ち受けるかのように押し黙った。
「あなたはもう子供じゃないんです。」意味深長にこういった校長は内心苛々し始めていた。
「はい、マダム。」素っ気なく、ほとんど楽しんでいるかのようにメシェールスカヤは応えた。
「といっても、大人というわけでもないんです。」校長はさらに意味深長にこう言うと、そのくすんでいた顔はほんのりと赤みを帯び始めた。「第一、その髪型はどういう事です? それは大人の女性がする髪型です!」
「マダム、私の髪質が良いのは私の責任ではありませんわ。」メシェールスカヤはこう答えると、きれいに整った自分の頭を両の手で危うく触れそうになった。
「なんとまあ、あなたは悪くないと言うんですか!」校長は言った。「あなたはその髪型に責任もなければ、その高価な櫛にも責任はないんですね、一足二十ルーブルもするパンプスでご両親に散財させていたとしても! でも、もう一度言いますが、あなたはまだ自分が一介のの女学生に過ぎないのだということすっかり見落としているのですよ…」
この時、メシェールスカヤは率直さを失わず、怯むこともなく突然、厳めしく校長の言葉を遮った。
「お言葉ですが、マダム、それは誤解かと思います。私は女です。この責任は誰にあるかご存知ですか? うちの父の友人で隣人、つまり、校長先生のご兄弟でもあるアレクセイ・ミハイロヴィッチ・マリューチンです。あれは去年の夏、田舎に行った時のこと…」
この会話の一ヶ月後、オーリャ・メシェールスカヤが属していた社会にはこれぽっちも共通点のない、見た目の野暮ったい平民風情のコサック将校が、到着したばかりの列車乗客でごった返すプラットホームで彼女を射殺した。そして、オーリャ・メシェールスカヤが校長を打ちのめすことになった信じられない告白が完全に裏付けられたのである。というのも、将校が法廷調査官に対して行った供述によれば、メシェールスカヤは将校をかどわかし、ねんごろの仲となった彼に妻になる誓いまで立てていたが、殺人のあった当日、ノヴォチェルカスクに向かう彼を見送りに来た彼女は駅で突然、自分は一度として彼のことなど愛したことなく、婚約話は全部彼へのからかいでしかないと告げると、マリューチンのことが書き綴られた日記のページを彼に読ませたというのだ。
「私はその文面にざっと目を通すと、おもむろに、私が読み終わるのをプラットホームでぷらぷら待っていた彼女に向けてぶっ放したんです。」将校はこう言った。「この日記、ほら、ここです。去年の七月十日のところを見て下さい。」
日記には次のように書かれていた。
《今、夜の一時。すっかり深い眠りについてたけど、ふと目が覚めてしまった…もう私は女になったのね! パパ、ママそれにトーリャたちはみんな街に戻って、ここに残ったのは私一人。一人になれて本当によかった! 朝は庭と原っぱを散歩、森に入ったとき、この世界には私一人っきりのように思えて、これまでの人生で最高だと思った。昼食も一人でとって、そのあとずっと一時間遊んだけど、音楽を聴いていたときの私、いつまでも終わりなく生きていくだろう、誰よりも幸せになるんじゃないかって気がした。そのあと、パパの書斎で眠り込んでから、四時にカーチャが私を起こしに来て、アレクセイ・ミハイロヴィッチが来たって教えてくれた。私は彼が来てくれて大喜び、彼を迎えて色々お世話できるなんてホントにご機嫌だった。彼が乗ってきた二頭立てのヴャートカ産の馬はとってもキレイで、玄関口に立ちんぼ、彼が家で休憩に立ち寄ったのは雨が降っていたからで、夕方までには体を乾かしたかったから。彼はパパがいなくてがっかりしてたけど、気を取り直して私のダンスのお相手をしてくれたし、私のことがずっと前から好きだったとか言って、さんざん冗談を飛ばしてた。お茶をする前に庭を散歩する頃には、また外も素晴らしい天気になって、すっかり寒くなったとはいっても太陽はすっぽり濡れそぼった庭のあいだをキラキラ輝いて、彼は私の腕を組み、自分はマルガリータを引き連れたファウストだとか言ってたわ。彼は五十六歳だけど、まだまだどうして素敵だし、いつも上品な身なり。ただ一つだけ身なりで気に入らないのは、家に来た時にトンビを羽織っていたことね、あれってイギリス製のオーデコロンの匂いがしてた。でも、眼はまだ若々しいし、黒々としてるし、髭は几帳面に長く二つに分けてあって、きれいな白金色をしてる。お茶を頂いたのはガラス張りのベランダ、なんだか気分が悪くなったので私は低い長いすに横になり、彼はと言うと、しばらくタバコを吹かしてから私の側に座り直すと、また色々と私のご機嫌をとる話を始めては、じろじろと私のことを見てから、手にキスをし始めた。絹の肩掛けで顔を覆うと、彼は肩掛け越しに何度か唇にキスをし…どうしてあんなことになってしまったのかしら、気が触れたんだわ、自分がこんな人間だなんて考えたこともなかったもの! こうなれば助かる方法は一つしかない…あの人に対する嫌悪感にはとても耐えられないわ!…》
この四月の日々が過ぎていくうちに、街はきれいになり、乾燥し、街角の石は白くなり、その上を歩くのも軽快である。毎週日曜日には礼拝後、街の出口に通じるソボール通り沿いに喪服と黒のライカ手袋に身を包み、黒檀製の傘をさした小さな女性が進んでいく。その女性が街道沿いに横断していく薄汚い広場には、煤を被った鍛冶場が数多くあり、そこを野原から爽快な空気が吹き込んでいる。その先をさらに行くと、男子修道院と城市のあいだに曇った天蓋は白み、春の野は灰色に色褪せて見えるも、修道院の外壁下にある水溜まりの隙間を突き抜けて左へ向きを変えると、そこで目にするのは白い菜園に囲まれた背の低い、広々とした庭のようなもので、その菜園の柵には聖母昇天と刻まれている。小さい女性は細かく十字を切り、慣れた足取りで小径を歩いていく。樫の十字架を前にしたベンチまで来ると、彼女は風吹きすさぶ春の寒さの中、薄手のブーツを履いた両足と窮屈なライカ手袋をはめた手がすっかり悴んでくるまで、一時間、二時間と座り込んでいる。春の鳥たちが寒さの中にあっても甘く歌うその声、陶製の花輪の中を唸り通る風の音を聞きながら彼女は時折、自分の命を半分呉れてやってもいい、せめて自分の目の前にはこの死者の花輪がなければと思う。この花輪、この墓丘、樫の十字架! まさか、十字架に嵌め込まれた、この隆起した陶製の肖像板から不死の光を眼光から輝かせているあの子がこの下にいるだなんて、それにこんなに純粋な眼差しを今やどうすれば一体、オーリャ・メシェールスカヤという名前と結びついたあの忌まわしきことと重ね合わせることが出来るのか? −しかし、心の底で小さい女性は、何かしら情熱的な夢想に身を捧げ尽くした人間たちと同様、幸福なのだ。
この女性はオーリャ・メシェールスカヤの担任教師で、若くはない未婚の女性、ずっと以前から現実生活をオーリャ・メシェールスカヤとすり替える妄想に生きている。この妄想の発端は、貧しくて、これといった取り柄もなかった准尉の弟で、彼女は自らの魂を丸ごと彼に、何故か彼女には輝かしきものに映じた彼の将来に、重ね合わせた。ムクデン郊外で彼が殺害された時、彼女は自らを理想的な働き者だと思いこんだ。オーリャ・メシェールスカヤの死は彼女を新たな夢想の虜にした。今や、オーリャ・メシェールスカヤは彼女を捕らえて放さぬ思考と感情の対象となった。彼女は休日ごとにメシェールスカヤの墓前に通い、何時間も樫の十字架から目を離さず、棺の中の花に埋もれたオーリャ・メシェールスカヤの顔色のない顔、それに、ある日立ち聞きしたことを思い出すのだった。それはこうだ。ある日の長い休憩時間のこと、女学校の中庭を歩いていたオーリャ・メシェールスカヤがお気に入りの友人で、体格がよくて背の高いスボーチナに早口でまくし立てるように喋っていたことだ。
「父さんのある本にね、父さんって古くて面白い本を沢山持ってるんだけど、女の美しさはどうあるべきかって書いてあるのを読んだの…そこにはね、ほんととても全部覚えきれないほど色々書いてあるのよ。まあ、もちろん黒々としてて、膠に煮えたぎる目ね、ほんとにそう書いてあったのよ。膠に煮えたぎる目よ! それに、夜の如く黒き睫毛、頬をたおやかに咲き戯れるもみじ、細やかなる体躯、人一倍スラリとした手、そうなの、人一倍ですって! それから、ちっさな足、そこそこ大きな胸、きれいな丸みを帯びたふくらはぎ、貝殻色の膝、撫で肩。私、沢山のことをほとんど暗記したほどよ。だって、書いてあることってみんな正しいんだもの! でもね、一番大切なことって何だか分かる? 軽い吐息よ! だって、私のってそうでしょ、ほら、聴いてみてよ私の吐息、ねぇ、言った通りでしょ?」
今やこの軽い吐息も再び世界に、この雲の広がる空に、このさめざめとした春の風の中に散ってしまったのである。